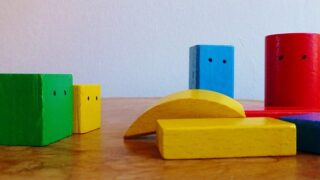こんにちは、私は元浪費家でアラサー主婦のゆうと申します。
産休に入る数ヶ月前から読書にハマっています。
幸い、自宅の近くに図書館があったのでしょっちゅう借りることができるのです。
図書館で借りればお金もかからず物も増えないし、知識欲が満たされ、良いことづくしなのです。
産休中の余暇時間に、ダラダラとSNSやYoutubeを見るより読書は有意義な時間を過ごすことができます(SNSもYoutubeも好きですが!)。
今回は、さわらぎ寛子著『言葉にする習慣』を読みました。
著者のさわらぎさんはコピーライターであり大学講師や会社代表取締役としても活躍なさっている方。
肩書だけでもすごい。
このタイトルを見た時、私はてっきり会話のテクニックに徹している本かと思ったんですよね。
私は面談や会議中に発言ができなくて落ち込むこともしばしば。
もし自分がすらすらと意見が言えたならどんなに良いか!
しかし最後まで読み終えると、人生における自分と他者とのあり方を見直すきっかけになりました。
自分の考えや思いをまとめる
もちろん、この本のタイトルから想像する通り会話での重要ポイントを丁寧に教えてくれます。
各章にワークシートが用意され技術を身につけられるよう促してくれます。
その中でも、私が自分の頭の中をまとめる上で特に参考にしたい!と思ったのが以下の項目です。
相手に求めるゴールは共感?行動の変化?
・「うまく言葉にできる」の“うまく“は状況と相手によって変わる。自分が得たいゴールを自分で明確にしておくとすれ違いが減っていく。
求められているのは意見?思い?
・その場でどちらが相応しいかによって、コミュニケーションのずれを防げる。
まとめる前に「広げる」
私は会議や面談の時によく「うまく言えない、考えが浮かばない!」と悩みますが、自分の思いや意見を言語化するためには頭の中だけでなく体を動かす習慣が大事なのだそうです。
体を動かすとは具体的に何をするの?と思ったら、
・思い浮かんだことをメモする。
・周囲や自分について観察をする。
・口に出して、またメモをする。
ということなんだそうです。
自分の中にあるモヤモヤ、違和感を掘り下げて言葉にするようになると自分や周囲へ深い理解ができるようになる。
また、うまく言葉にできない時も「言いたいことは浮かんでいますが、うまく言葉にできません」等、普段から素直に自分の状況を口に出して説明する練習をしていると「えっと…」と止まらずに言葉が出るようになっていくそうです。
予習・復習をする
・「あの時、ああ言えば良かった」と振り返った時はそのシーンに戻ったつもりで口にだしてみる。
・予定がある場合も相手をイメージしながら自分のセリフを口にだして言ってみる。
説得力と納得感のある意見とは?
・前提(自分の立ち位置・言葉の定義)、考え、根拠(理由・ファクト・体験談)の3つの要素が揃っていること。
前提を定義する
・自分の立ち位置を決めると同じ事象でも意見は変わる。
・言葉の定義を決めておくと話が噛み合わないことが防げる。
相手に伝える
自分が言いたいことを相手の知りたいことに変換する
・自分の言いたいことをそのまま言っても相手の気持ちが動くかは別問題なので工夫が必要である。
こちらの発言に対して、相手はそれが「自分にとってどういいか」「他のものとどう違うのか」「それで気分が上がるか、惹かれるか」を知りたがっている。
相手が何に惹かれるか・興味があるか観察をして、自分の言いたいことを相手が知りたいことに変換し相手の反応を得る。
誰に、何のために、相手にどんな反応を望むか
・相手に伝える前に「誰に、何のために、相手にどんな反応を望むか」の3つに立ち返る。
同じ内容でも相手の理解度、興味の度合い、相手が知りたい順番を相手に合わせる。
全体像→詳細の順に伝える
・ざっくり概略から伝えて、詳細を話す。何の話をしているのか分かりやすくするため。
具体的な言葉で依頼する
・して欲しい行動は具体的に伝える。
言葉にできる力がもたらすもの
個人的に、終章を読み自分自身の捉え方や相手との向き合い方が今後変わってくるなと思った。
人生の主語を自分にする⇨自分の人生を自分の意思で変えられる
・「〜された」「〜してくれない」は受け身の発想で、自分は何かをされる側になっている。
自分が被害者ポジションである方が自分から動かず外野から不満を言うだけで楽。しかし「自分はこうしたい」「自分はこう思う」と自分を主語にして語らないと自分の思いは伝わらない。受け身に慣れると自分が他者にコントロールされる側と諦め、自分の人生を自分の意思で変える力が弱まる。
自分を知る⇨相手を知る⇨自分と相手に優しくできる
・「相手が大切にしているもの」を見ずに、「自分が大切にしているもの」を押し付けているとコミュニケーションエラーが生じる。
良かれと思って相手にしたことが受け取ってもらえない時や、言いたいことが伝わらないときは相手と自分で「大切にしているもの」が違う可能性がある。
まず自分の「大切」を知ると自分という人間を知れて、相手にも「大切にしている世界」があるとわかる。
相手が何を大切にして守りたいのかを考え、意見の折り合いをつけられれば自分と相手の双方を大事にできるコミュニケーションが取れる。
自分とは何か⇨自分を定義する言葉で自分を縛っていることに気づく
・自分の長所も短所も全て自分だが、どこに注目するかは自分で選べる。
短所に目が行きがちだが、自分を言葉で定義して自分を縛っているだけかもしれない。
例えば、「私は神経質」と思っているからそのように行動しているだけかもしれない。
読了後、自分に組み込みたいことは?
日常生活で「あ〜モヤモヤする!」という場面はよくあります。
そのモヤモヤを深掘りしてみると「私はこういう状況や対応にストレスを感じるのだ」と言語化され(自己分析され)、少し視界が良くなる気がする。
「こういう状況にストレスを感じるなら、じゃあ次はこちらも対応を変えてみよう」と対処できるわけだし、「モヤモヤ」をそのままにしないことが自分を大切にすることにつながります。
日頃から頭の中から思考を出す作業が習慣づけば、自分の感情や考えを言語化することにつながる。
私はよくノートに考えをまとめるけれど、口にだしてみる作業はしてきませんでした。声に出して考えを述べる練習ができていないものが、本番(会議や面談)においてできるはずがありません。
それから、コミュニケーションにおいては“相手がいる“。
自分の思い・考えを押し付けるように話しかけても、相手も望むものでなければに響くことはない。
そのことを念頭にコミュニケーションを取る必要があると学びました。
・まずは焦らず自分の伝えたいことが何かを考えてみてメモや声に出してみる。
・すぐに浮かばなくても慌てずにその状況(考えが浮かばない状況)を話してみること。
・うまくまとめようとしないで(頭の中で広げた中でも)一番言いたいことを言ってみること。
上記をまず実践してみようと思います。